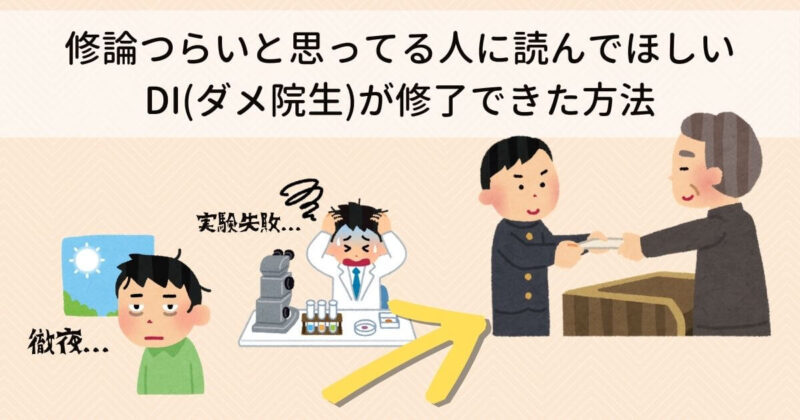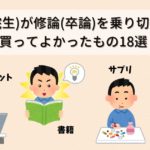もう逃げ出したいなぁ。
ポイント
こんなお悩みを抱えている方の悩みを少しでも解消します。
この記事に辿り着いた方は、「修論 辛い」や「修論 やばい」と検索した方かと思います。
本記事は、そんな修論が辛くてたまらない方、今すぐ逃げ出したい、そんな方向けです。
DI(ダメ院生)だった管理人が修論を乗り切った方法を解説します。
この記事の目次(クリックでジャンプ)
修論つらいと思ってる人に読んでほしい DI(ダメ院生)が修了できた方法


修士課程から新たな研究を進めることになったので、修士1年では全然研究が進まず、修士2年後期から本気を出して、なんとか修了することができました。
本記事では、DI(ダメ院生)だった私の体験談をご紹介します。 この記事を読んで、少しでも修論に対する不安な気持ちが解消すれば嬉しいです。
結論、
- 修士2年後期は、週7で研究室に通う。
- 風呂・睡眠以外は研究室で過ごす。
- ゼミ前は二徹(二日連続徹夜)。
- 修論執筆は、可能な限りアウトソーシングを活用する。
- 修論発表会は、「できるものなら留年させてみろよ?」のマインドで乗り切る。
私はこのような方法・マインドで修了することができました。
それでは、詳しく解説していきます。
DI(ダメ院生)が修了できた方法① 修士2年後期は週7で研究室に行く

この記事を読まれている方は、修論がつらすぎて、研究室に行きたくない方がいるかと思います。中には、すでに不登校となっている方もいるでしょう。
ココがダメ
研究が進まない ⇒ 教授に怒られる(ゼミで叩かれる) ⇒ 研究室に行きたくない
そんな方はこのような悪循環に陥っていると思います。
私も修士1年では全くといっていいほど研究が進まず、結果が出ないため研究計画のみをゼミで発表するようなダメ院生っぷりでした。
教授達からは、「何で結果が無いんだ?」「研究が退化していないか?」などと叩かれました。
先輩、同期、後輩、皆の前にこのように叩かれ、私の自尊心はボロボロとなり、研究室に行くのを辞めました。
こうした経験から家で研究をすることにしましたが、パソコンを開けばYouTubeで作業用BGMを探し、気づけば動画をずっと見ている、こんな生活を繰り返していました。
家にいても全く研究が進まないので、まずは環境を変えようと、深夜帯に研究室に行くようになりました。
幸い、同期とは仲が良かったこともあり、研究室に行くのが苦にならなくなりました。これは恵まれていたと思います。
太陽とともに寝て、月とともに起きる生活を繰り返した結果、自律神経がぶっ壊れそうになり、徐々に朝型へとシフトさせました。
最初は教授と顔を合わせるのが嫌でしたが、人間とは不思議なもので、徐々に慣れていきました。
そのうち、研究も進むようになり、週7日研究室に通うようになり、結果的に修了することができました。
こんな経験から以下の学びを得ることができました。
- 強い意志が無い限り家では研究が進まない。黙って研究室に行くべし。
- 研究室での生活が中心になれば、教授への嫌悪感も無くなる。
- 研究室で週7日も過ごせば、進捗もそれなりに出てくる。
ところで、
卒論は「参加賞」、修論は「努力賞」、博論は「勲章」と言われています。
「修論=努力賞」ですよ。頑張れば、修了できるんです。
教授は凄い成果を求めている訳ではないのです。頑張っている姿勢を見せ続ければ、それなりに助けてくれるはずです。
特に修論の追い込み時である修士2年後期は、私と同じように週7日研究室に行くことをおすすめします。
研究室に週7日行くことで、あなたは研究室だけの生活になります。
朝起きたら研究室に向かい、3食研究室で食べ、眠くなったら自宅に帰る。
こんな生活をしてみてください。これくらい追い込めば、余裕で修了できます。
週7で土日祝日関係なく研究室に行けば、それなりに研究も進みますし、頑張っている姿も教授に見せることができます。
具体的に言うと、私の修論の8割は修士2年での研究成果となります。修士1年での進捗はほとんどありません。
こんな私でも修了することができました。
研究室に行くのがどうしても不安な方や憂鬱な方は、こんなサプリメントがありますので、試してみてください。
ココがおすすめ
研究室に行くのが嫌で嫌で仕方ない時期はこのサプリを多用してました。少しは気分がほぐれましたよ。
このような修論執筆時に役立ったものについては、以下の記事で解説しています。
-

DI(ダメ院生)が修論(卒論)を乗り切るために買ってよかったもの18選
続きを見る
DI(ダメ院生)が修了できた方法② 風呂・睡眠以外は研究室で過ごす

前述の通り、私は修士2年の後期は週7日研究室に通っていました。
目が覚めると、寝間着に防止を被り研究室に行き、腹が減ったらコンビニで飯を買い研究室で食べる。
眠くなったらレッドブルを飲み眠気を覚ます。(レッドブルは箱買いしてストックしていました。)
こんな生活をしていたので、大学に設備の無いシャワーと寝床以外は研究室で過ごしていました。
これだけ修論に時間を投じたので、最終的な研究成果に後悔はありませんし、やりきったと胸を張って言えます。

こんな生活できるのは、学生のうちだけです。
人生一度きりです。後悔のないようにしましょう。
DI(ダメ院生)が修了できた方法③ ゼミ前は二徹(二日連続徹夜)

週7日研究室に通い、おまけに風呂と睡眠以外は研究室で過ごすようになった私ですが、やっぱりゼミ前は追い込まれました。
ゼミに向け計画を立ててもうまく進まないことも多々あり、最終的には徹夜で乗り切ることが多かったです。
修士2年でよくやっていたのが二徹(2日連続徹夜)です。
諦めが悪いDI(ダメ院生)な私は、ゼミが近づくにつれ、

あ、これも結果の妥当性を主張するには必要だな。
とやることを増やしていき、ゼミ直前でパワポもレジュメも仕上がっておらず、これをなんとかするべく、二徹で乗り切っていました。
二徹したことがある方は分かると思いますが、頭痛や関節痛が凄まじく、とても研究発表するようなコンディションではありません。
ふらふらな状態で発表・質疑を乗り切り、即帰宅し布団で寝ていました。
今、修論に取り組んでいる方は、こうならないようにしましょう。
DI(ダメ院生)が修了できた方法④ 修論執筆は可能な限りアウトソーシングを活用する

修論執筆ってかなりの労力を使いますよね。
私は執筆ギリギリというか執筆中まで修士研究を継続していました。
こんな方多いのではないでしょうか。
ぶっちゃけこんな状態で、修論執筆に注力することは難しいですよね?
私も研究の合間に修士論文を執筆することに限界を感じていました。
そんな中思いついたのが、修論の執筆にアウトソーシングを活用すること。

お金で解決できるものはお金で解決しちゃいましょう。
アウトソーシングといえば、聞こえは良いですが、ただの「外注」です。
ここで、修論でアウトソーシングできるものとして、英文アブストラクトの執筆が挙げられます。
英語が得意な方はすぐ書けますが、苦手な方は数日かかってしまう、そんな英文アブストラクト。
留学生や外人の先生があなたの研究室にいれば、真っ先に翻訳を依頼することをおすすめします。
ココがおすすめ
頼れる方がいない場合には、「翻訳代行」サービスを活用し、アウトソーシングすることをお勧めします。案外安いですよ。
見積だけでも取ってみると良いと思います。
私の修論の英文アブストラクトは、ほとんど翻訳代行で執筆してもらいましたが、教授に指摘されることもなく、時間を節約することができました。
ちなみに、管理人の修論執筆期間は1か月半、総文字数は43,000文字、総ページ数132ページでした。
修論執筆の目安にしてください。
DI(ダメ院生)が修了できた方法(マインド)⑤ 修論発表会は「留年させてみろよ?」のマインドで乗り切る

ここまで私が修論を乗り切ることができた方法を書きましたが、もう最後はマインドしかありません。
特に、最後の大舞台である修論発表会って、とんでもなく緊張しますよね?
私もそうでした。緊張して前日もなかなか寝付けなかったです。
でも、修論発表会で発表できる段階まで研究を進めることができれば、修了できると思います。
ぶっちゃけ、教授も留年させるの面倒ですし、できるだけ修了してほしいのです。
冒頭書いた通り、「修論=努力賞」なんです。
凄い成果はなくても、それなりの成果があれば、修了させてくれますよ。
むしろ、「出来るものなら留年させてみろよ?」くらいのマインドで修論発表会に臨むと良いです。
その方がおどおどせずに、堂々と発表できると思います。
もし、修論発表会が不安で仕方ない方は、以下のようなグッズがありますので、お守り代わりに持っておくと良いです。私も同じものを買いました。
首などにかけておいて、作動させておけば、鼓動のような振動で自然とリラックスできます。
修論発表やゼミ、学会発表では常に携帯していましたが、周りにも気づかれることはありませんでした。
発表で手が震えてしまう方や、どもってしまう方は購入を検討してみるとよいでしょう。

まとめ
本記事では、DI(ダメ院生)だった管理人が修了することができた方法をご紹介しました。
- 修士2年後期は、週7で研究室に通う。
- 風呂・睡眠以外は研究室で過ごす。
- ゼミ前は二徹(二日連続徹夜)。
- 修論執筆は、可能な限りアウトソーシングを活用する。
- 修論発表会は、「できるものなら留年させてみろよ?」のマインドで乗り切る。
このような方法・マインドで無事に修了することができました。
この記事をご覧になられている方は、修論に追い込まれている方だと思います。
研究職にでもならない限り、研究できるのは学生だけです。
この機会をポジティブに捉えて、修士研究に取り組みましょう!

あなたが修了できるよう応援しています。
合わせて読みたい